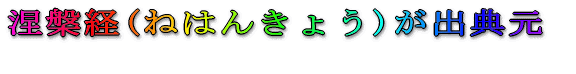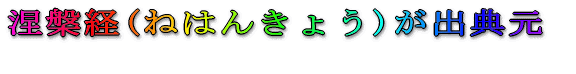|
祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。
沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理(ことわり)をあらわす。
驕(おご)れる者久しからず、ただ春の夜の夢の如し。
猛(たけ)き人もついに滅びぬ、ひとえに風の塵に同じ。
|
| ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
 |
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑひもせす
|
色は匂へど 散りぬるを
わが世誰そ 常ならむ
有為の奥山 今日越えて
浅き夢みじ
酔ひもせず
|
|
消失を意味するインドの言葉を漢字で発音表記したものが涅槃(ねはん)といい、仏陀の死の意という。仏陀は諸説あれど紀元前463から383年の人。同時代にはソクラテス、プラトンがいる。
仏陀はガンジス川沿いを四十五年もの間放浪の旅を続け、対機説法という、ひとり一人に合った教説を説き、自らは教説を書物にすることなく、クシナガラの沙羅双樹の下で弟子たちに見守られながら80年の生涯を閉じたという。
仏陀入滅後弟子たちにより、口伝えに伝承され、その後書き物にて伝承され、三世紀から四世紀にかけて大乗仏教という新たな仏教のもとで大乗涅槃経は、成立したもののようです。
祇園精舎の無常堂(病僧のための建物)の四隅にある鐘は、病僧の臨終のときには自然に鳴りだして、「諸行無常 是生滅法 生滅滅已 寂滅為楽」と説いたという。病僧はその鐘の声を聞いて、苦悩を忘れて臨終を迎えることができたということから、平家物語のこの文は作られたと言われる。
いろは歌は無常観を歌った極めて仏教的な内容の歌である。新義真言宗の祖である覚鑁(かくばん、1095年7月21日-1144年1月18日)は『密厳諸秘釈(みつごんしょひしゃく)』の中でいろは歌の注釈を記し、いろは歌は世に無常偈(むじょうげ)として知られる『涅槃経』の偈「諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅為楽」の意であると説明した。
|
|